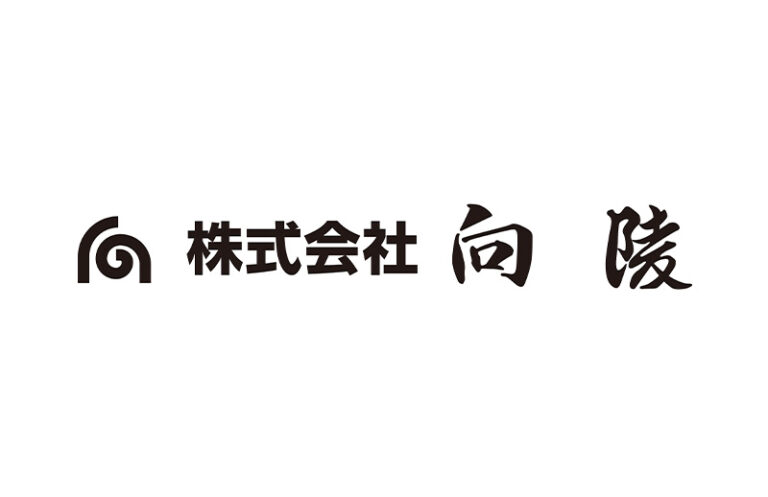-
経営理念
私たちは、この世の「もったいない」を追求し、常に革命の志を持って進化し続け、持続可能な地域社会作りに寄与します。
『私たちは、この世の「もったいない」を追求し、常に革命の志を持って進化し続け、持続可能な地域社会作りに寄与します。』
RE:ARTHでは『見直す』をコンセプトに、資源や地球環境、私たちの生活や未来をもう一度見直し、より良き地球環境を未来に繋げられる取り組みを事業としています。
地球で生活する生命体のうち、ごみを出しているのは人間だけです。そのごみが原因となり、地球という同じコミュニティに生息する他の動植物の生態系に大きな影響を及ぼしています。しかし、この「ごみ」とは、現在の人々の都合で処理できない、あるいはされないものが「ごみ」として処分されているのです。そのため、その「ごみ」をもう一度見直し、使えるものを活用し、少しでも「ごみ」を減らしていくことこそが、地球というコミュニティに住まうメンバーの務めであると考えています。資源活用のヒントはいろいろなところに転がっています。それらを拾い集め、組み合わせることで新たな解決法を導き出せるのだと思います。それを私は革命と呼んでいます。
私たちのビジョンに「Revolution is Evolution(革命は進化だ)」という言葉があります。小さな資源活用の革命が幾重にも重なり、やがては大きな社会の進化につながっていく。そのような思いが込められています。
RE:ARTHがこの経営理念にたどりついたのは、代表の倉橋が「ブルーエコノミーに変えよう(著:グンター・パウリ)」に出会ったことから始まりました。ブルーエコノミーでは地球のあらゆる生態系から学び、実践される環境循環型経済モデルの事例が数多く紹介されていました。そのなかで、コーヒー残渣からきのこを栽培するという事例がありました。このプロジェクトを進めていたのがChido Goveraさん(The Future of Hope Foundation創設者)でした。倉橋は彼女に会い、活動に参加するためにジンバブエに渡りました。ジンバブエでは、通常キノコ栽培に使われる稲わらや木くずなどの資材はおろか、コーヒーの消費量はとても少ないため、これらの資材を使ってキノコを栽培することは不可能でした。しかし、Chidoさんは人々の主食であるトウモロコシの芯や、いたるところに落ちている落ち葉、どれだけ貧しいコミュニティーにも1頭はいる牛の糞を使用し、キノコを栽培していました。このプロジェクトにより、多くの貧しい人々が食べることに困ることのない生活を実現できるようになっていました。倉橋は地域の特性を注意深く観察し、分析することで、あらたな資源を発掘することができることを知りました。
日本はジンバブエのような開発途上国に比べると、多くの資源が溢れている社会です。そして、日本で生産できないものは外国からたくさん輸入しています。そのような物資の移動距離はとても大きく、ものの移動距離が延びればそれだけ多くの資源が消費されます。だからこそ、私たちはそういったものをできる限り使い切り、有効に活用する努力をすべきだと私たちは考えています。そのために、私たちは常にこの世の「もったいない」を追求する努力が必要と考え、私たちの理念としています。
-
経営理念に基づいて、具体的に取り組んでいること
京都市内で出るコーヒーカスを使用してきのこを栽培しています
RE:ARTHでは、京都市内で出るコーヒーカスを使用してきのこを栽培しています。
京都の一人当たりのコーヒー消費量は日本で一番多く、京都には独特のコーヒー文化があります。また、日本国内で消費されるコーヒーの99%以上はブラジルやケニアなどの南米およびアフリカの国々から輸入されています。にもかかわらず、1杯のコーヒーに含まれる実際に使われるコーヒー豆の成分は0.2%と言われており、残りの99.8%を私たちは「カス」と呼んで廃棄しています。
この「もったいない」コーヒーカスの現状を打開すべく、RE:ARTHではコーヒーカスを使ってキノコを栽培しています。また、キノコ菌の力により菌床内のコーヒーカスの分解が進むため、キノコを栽培した後の菌床は堆肥として活用可能です。
このような取り組みはアメリカやヨーロッパではいくつか見られますが、日本では先行事例がありません。これは、日本のキノコメーカーのいくつかがコーヒーカスを用いた栽培実験を行ったのですが、1菌床あたりの収穫量が事業化するレベルに至りませんでした。そのため、各社撤退してしまい、日本ではコーヒーカスを使用したキノコ栽培の技術が発展することはありませんでした。しかし、RE:ARTHでは一般のキノコ生産者が通常使用する施設や資材をほとんど変えることなく、コーヒーカスを使用した栽培に成功しました。そのため、この栽培方法は新たな投資等をほとんど必要とせず、ビジネスモデルの拡散により、急速に全国に広めることが可能な点が、このプロジェクトの革新性です。
-
今後のビジョンや展望など
日本各地にコーヒーカスの小さな循環を起こす
RE:ARTHの今後のビジョンは、このコーヒーカスの循環を京都で実現し、そのビジネスモデルを全国に広めることで、日本各地にコーヒーカスの小さな循環を起こすことです。
コーヒーは全国に流通しており、各地で飲まれています。同様に、キノコ生産者と消費者も日本全国にいます。そのため、各地のキノコ生産者に栽培ノウハウを伝えることで、日本各地でコーヒーをキノコ栽培に活用する小さな循環が日本各地で巻き起こることになります。
また、キノコ栽培を終えた菌床を他の農業者に無償でゆずることで、農業者の資材コストを削減し収入の向上を実現することで、新たな農業の担い手発掘に貢献できます。
上記に加え、RE:ARTHでは農福連携にも取り組んでいきます。私たちは農業が繰り返しの作業が中心であることから、人生において選択肢が少ない人々、つまりは障害者や難民に働く機会を提供できると考えています。特にキノコ栽培では、身体的負担が少なく、シンプルな作業を繰り返すことが多いため、それぞれの特性に合わせた作業に従事していただくことが可能です。また、一般的な農業に比べて季節ごとに仕事量や仕事内容が変化しないため、1年を通して継続的な雇用の実現につながります。
コーヒーカスは一般的に廃棄物と認識されています。そのため、廃棄物処理業などの認可を含む廃棄物処理法などの法令により、多様な事業者がそのリサイクルに取り組むことが困難です。現に、RE:ARTHに寄せられる多くのお問い合わせが、廃棄物とされるコーヒーカスの収集運搬をどのようにしているのか、というものです。この点に関して、RE:ARTHでは現在京都市と調整し、コーヒーカスを廃棄物の範疇からどのように外すことができるかを検討中です。この点をクリアにすることで、コーヒーカスの集め方、栽培方法、資源循環の仕組みを京都から全国に発信することが可能となります。
また、コーヒーカスの循環に参加したい生産者だけでなく、キノコを買いたい顧客や菌床を使いたい農家の情報ハブを作りたいと考えています。そうすることで、新たに参入したいと考えるキノコ生産者に、コーヒーカスの入手先、栽培方法、販売先、使用済み菌床の受け入れ農家などを紹介することが可能となります。
私たちは農福連携への取り組みやコーヒーカスを資源とみなす仕組み、その資源の循環に参画してくださる人々の情報の集積をすることで、この活動がよりスピーディーに拡散していくと考え、このビジョンを共有しています。
-
取り組みにより、どのような社会的インパクトを起こしてきましたか
東京や栃木、名古屋、大阪などで3社1自治体へ広がり始めています
RE:ARTHのコーヒーカスを使用したキノコ栽培は全国的にも珍しく、大きな社会的インパクトを起こしています。
現在のRE:ARTHが所有する栽培ハウスは全長がたったの10メートルしかありませんが、このハウスで年間26トンものコーヒーカスを使用してキノコを栽培しています。また、そこから生産されるキノコの量は年間500kgを超えます。そのため、小さなスペースでもこの取り組みに参画できると様々な事業者に認識いただいています。
また、当方の取り組みはテレビや新聞、ラジオなど多くのメディアで取り上げられてきました。それだけ現代の社会に合った取り組みと認識してもらえていると感じています。
そして、当方で栽培したキノコを取り扱ってくださるお客様も、大手ホテルチェーンや有名飲食店などが急増しており、当方の取り組みが社会に与えているインパクトを再認識しているところです。
まず、当方の取引先として、最近では大手ホテルチェーンからの問い合わせが増えています。その多くが、ホテルで出たコーヒーカスを当方に引き取ってほしいというものだけではなく、そのうえで栽培したキノコをホテル内のレストランで顧客に提供したいというものです。そうすることで、この活動はホテルとRE:ARTHの間に留まるのではなく、ホテルを利用する人々にも波及していき、一般の方々にもコーヒーカスでキノコが栽培できることを知っていただける機会へとつながっています。
また、京都で最大級のコーヒーメーカーでも当方のキノコをご利用いただいています。コーヒー屋さんにはコーヒーに関心のある人たちが多く集まります。そのような人々に当方の活動を知っていただいくことで、より認知度が向上し、活動が広がりやすくなると信じています。
そして、このような当方の活動を知っていただいた方々からの相談も増えています。
現在、計画の段階から相談に乗っていた事業が、大阪でスタートしています。また、東京や栃木、名古屋、大阪などでも3社1自治体がこの取り組みを関東や大阪でも実現するために動き始めています。これらすべてのプロジェクトを総計すると、年間200トンを超えるコーヒーカスの再利用が実現することになります。
RE:ARTH単体でなくとも、広がりやすい仕組みを考えたことで、ネットワークとしてより多くのコーヒーカスを再利用できるようになってきました。
-
今後のビジョンや展望により、どのような社会的インパクトが期待できますか
持続可能な農業と障害者雇用のモデルに
今後のビジョンや取り組もうとしていることで、社会的にコーヒーカスがごみではなく資源とみなされることが期待されます。また、障害者雇用が進むだけでなく、サービス業を営むホテルや飲食店がオリジナルのキノコを生産するようになることが期待されます。
RE:ARTHでは、京都にコーヒーカスを使ったキノコの菌床センターをつくりたいと考えています。そうすることにより、毎週約2トン、年間で約100トンのコーヒーカスを京都市内で循環させることができ、毎週約700kgのキノコを生産することが可能となります。これらを、京都市内の飲食店やスーパーでお取り扱いいただくことにより、京都はコーヒーの消費量だけでなく、そのリサイクルまで日本一だと言われるようなインパクトを生み出したいと考えています。
また、現在の全国からの問い合わせ状況を鑑みると、5年以内には全国で200トン以上のコーヒーカスをキノコ栽培に使用することができるようになると考えています。主に東京や大阪などの首都圏でこれらのプロジェクトが認識されることにより、その影響は全国に波及します。
RE:ARTHの農福連携は、農業分野で障害者の安定的な雇用を生み出すことに大きく寄与します。きのこ栽培は、単純かつ繰り返しの作業が多く、通年での安定した生産が可能なため、障害者にとって働きやすい環境が整っています。これにより、障害者の社会参画が進み、彼らの経済的自立を支援することができます。さらに、障害者雇用が促進されることで、地域の福祉的な側面が強化され、インクルーシブな社会づくりに貢献します。
また、きのこ栽培後に残る菌床を堆肥として地域の農家に提供する取り組みは、農業コストを削減し、持続可能な農業を支援する重要な要素となります。特に資材費の高騰に苦しむ農家にとって、このような再生可能な資源を利用することは、経済的負担を軽減し、地域の農業を持続可能にします。そして、収穫体験などを通じ、食育や環境教育の一環として、子どもたちや地域住民に資源循環の重要性を伝えることができます。きのこ栽培プロセスを通じた環境教育は、未来を担う世代に対し、循環型社会の意識を高める教育的インパクトを与えることが期待されます。
環境、福祉、食、教育にアプローチできるRE:ARTHの取り組みは、持続可能な農業と障害者雇用のモデルとして日本全体に影響を与える可能性があります。他の地域や企業がこのモデルを採用することで、持続可能な資源利用と包摂的な社会が広がっていきます。
-
従業員・顧客・取引先への配慮
従業員との毎日のコミュニケーションを大切に
社会および取引先での資源を再考し、コミュニケーションを密にすることで資源を最大限活用できるようにしている。
また、RE:ARTHは大変小さな組織なので、従業員と毎日コミュニケーションをとることで、差別の禁止、異なるバックグラウンドをもつ人たちへの理解、働きやすい環境とな何なのかを相談しながら組織作りに取り組んでいる。 -
地域社会への配慮
地域の活動に、経済、教育、福祉の面からアプローチしています
現在、RE:ARTHでは京都市内で回収したコーヒーカスを使用して、京都市内でキノコの栽培に取り組んでいます。収穫したキノコは主に京都市内の事業者や消費者に販売し、地域内での資源循環を目指しています。このプロジェクトを通じて生産したキノコを地域の人たちに消費してもらうことで、地域内での資源循環から生まれた食品に愛着を持ってもらえるように心がけています。
また、当方ではインターネット販売等はしておらず、地域内での消費に限定することで、地産地消を心がけています。
RE:ARTHでは、地元のボランティアグループへのサポートにも取り組んでいます。これは、ボランティアさんなしには当方のコーヒーカスの回収スキームを実現できないためです。また、このボランティア活動を通じて知り合った人々のなかで情報共有がなされ、新たな活用資源の発掘と、資源活用の結果としてできた野菜やキノコを購入してくれるあらたな取引先の確保にもつながっています。
また、代表の倉橋は高校と大学でラグビーをしており、スポーツの教育的意義を信じています。しかし、近年では家庭の経済的理由からクラブ活動を続けられない学生が多いと顧問の先生から伺い、京都府立向陽高校のラグビー部のスポンサーになることを決めました。寄付ではなくスポンサーという形を選んだのも、学生たちに部活の運営に積極的にかかわってもらい、高校の段階からビジネスに触れてもらいたいという思いからです。
以上のように、RE:ARTHでは地域の活動に、経済、教育、福祉の面からアプローチしています。 -
環境(未来の社会)への配慮
太陽光パネルを設置した自家発電自家消費システム
RE:ARTHでは主に、栽培ハウスでの電力消費を懸念しています。そこで、太陽光を必要としないキノコ栽培だからこそ可能な、ハウス上面に太陽光パネルを設置した自家発電自家消費システムを検討しています。
また、再利用不可能なプラスチック製品等は産業廃棄物として適切に処理しています。プラスチック製品の再利用を目的として、キノコのボトル栽培(牛乳瓶のような使いまわし可能なボトルをつかったキノコ栽培)にも挑戦中です。