「文化×ビジネス」の可能性を切り拓く人と、その活動を支援する人が混ざり合って考えたこと ~カルチャープレナー(文化起業家)交流会レポート~

2023年よりForbesJAPANが選出している、CULTURE-PRENEURS 30。
カルチャープレナー(文化起業家)とは、文化やクリエイティブ領域の活動で新しいビジネスを展開し、豊かな世界を実現しようとする人たちを表す、新しい概念です。
2024年10月には、京都市と共に、上京区の上七軒歌舞練場で授賞式イベントを開催。「これからの1000年を紡ぐ企業認定」のコンセプトとも共通する部分があり、これまでに認定企業から下記5名がカルチャープレナーに選出されました。
株式会社Casie 藤本 翔 さん
株式会社水星 龍崎 翔子 さん
株式会社堤淺吉漆店 堤 卓也 さん
株式会社Dodici 大河内 愛加 さん
有限会社斗六屋 近藤 健史 さん
2025年3月21日、堀川御池ギャラリーで開催された交流会にSILKメンバーも参加させていただきました。当日の様子をご紹介します。
—

京都市が初めて開催した、カルチャープレナー交流会。
参加者はカルチャープレナー28名に、その活動に関心を寄せる支援機関や教育機関、行政などのメンバーを加えた総勢約89名。
「どうすればカルチャープレナーは、もっと活躍することができるか?」をテーマに、必要な支援のあり方などを、対話を通じて参加者の皆さんが考えた模様をレポートします。
カルチャープレナーに向けられている熱い視線

開始前から会話が弾む様子が会場のあちこちで見られ、熱気ムンムンの中、スタートした交流会。
「奇跡のようなタイミングが重なり、カルチャープレナーの方々にフォーカスした取組を始めることができました」と冒頭の挨拶で話すのは、京都市の覚前さん。
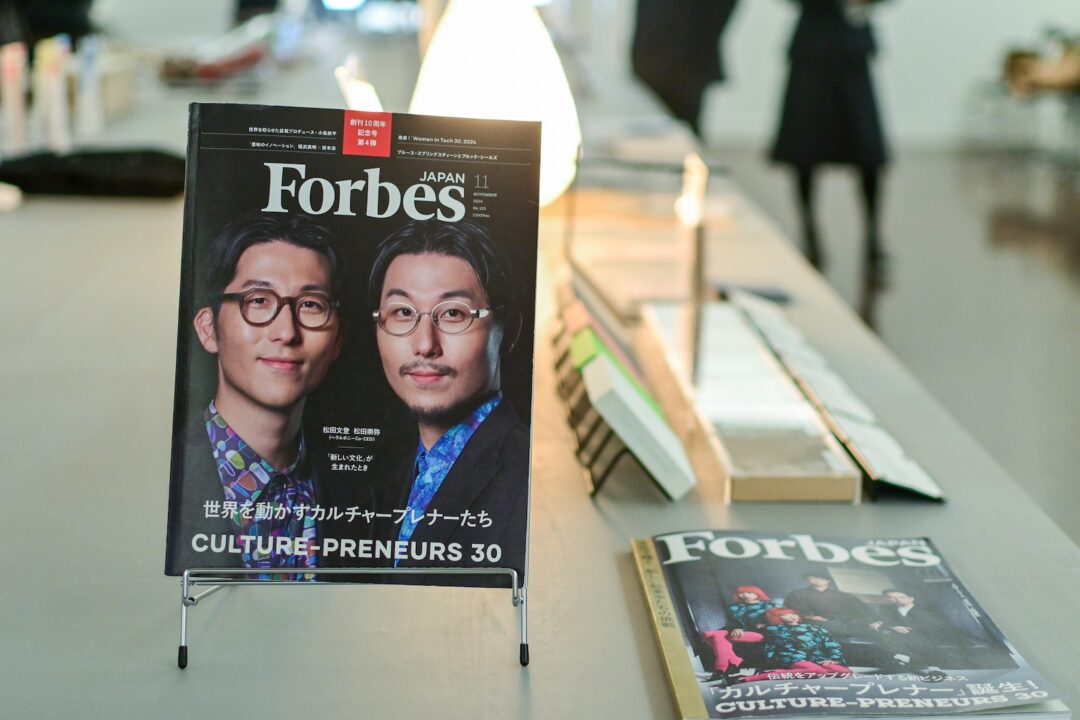
京都市がカルチャープレナーに着目したのは、さかのぼること2年前。「KYOTO Innovation Studio」という、有識者と京都市が意見交換する事業の中で、「京都はカルチャープレナーの聖地を目指すべきではないか」という提言を受けたことが、きっかけだったそう。
時を同じくして、カルチャープレナーの存在に注目していたビジネス誌ForbesJapanと、「ならば資金面での支援を」という三井住友信託銀行、そして京都市の三者の想いが合わさり、カルチャープレナーを表彰する「CULTURE-PRENEURS AWARD(カルチャープレナーズアワード)」が誕生。2023年、2024年と2年連続で開催され、さらにカルチャープレナーと関係する人たちのコミュニティが作れたらと、今回の交流会の開催に至りました。

覚前さんの挨拶に続いて、交流会の企画・運営を担当する、株式会社よい根の前田さんから、カルチャープレナーを取り巻く近年の動きについて、紹介がありました。
カルチャープレナーを応援する団体や場が、京都で一つ、また一つと芽生えている今だからこそ、「今日は皆さんと一緒に、分野を超えた交流を通じて、カルチャープレナーへの支援の機運をさらに高めていけたら」と話す前田さん。
交流会をきっかけに、カルチャープレナーの皆さんの活躍の場がさらに広がっていきそうな予感にワクワクしてきたところで、トークセッションへ移ります。
「支援」には様々な形がある?

登壇されたのは、
一般社団法人日本カルチュアプレナー協会 代表理事 足立 毅 さん
株式会社Casie 取締役 清水 宏輔 さん
株式会社水星 代表取締役CEO/Creative Director 龍崎 翔子 さん
のお三方。
清水さんや龍崎さんはカルチャープレナーとして、そして足立さんは支援者として、それぞれの目線で過去に経験した支援の事例や、これからの支援のあり方について、前向きな意見が交わされました。

絵画のサブスクリプションサービスや、海外への日本のアート作品の流通を手がける株式会社Casie。「アーティストが活躍する場を作っていく」という会社のミッションに対して清水さんは、「スタートアップとしての側面から、IPOや出口戦略といった『数字』の結果を求められがちな部分に、難しさや寂しさを感じています」と話します。
「もちろん、求められる『数字』の成果をしっかり出すためにきちんと計画を立てて事業に取り組んでいます。その中で、チャレンジする機会を『支援』という形でいただけるとありがたいなと思います。最近は、海外から日本へ来られている方に向けて、作品を展示することが多く、展示内容に合った公共空間を使う機会をいただけるとうれしいですね」

「資金面での支援は、もちろんありがたいのですが」と前置きしつつ、清水さん同様、ソフト面での支援の事例をお話されたのは、株式会社水星の龍崎さん。「メディアとしてのホテル」を掲げ、独創的なクリエイティビティで、京都をはじめ全国各地でホテルを経営されています。事業を通じて、「この場所を上手く活用できないかな?」、「こんなイベントをしたいけどホテルを使えへんの?」と寄せられる相談がアイディアの種になり、新しい事業へつながることが多々あるのだそう。
「自社の事業に関連する、誰かのちょっとしたリクエストをお聞きできるような機会が支援としてあれば、とてもうれしいです」と、笑顔で話します。

2024年11月に、カルチャープレナーの支援団体として、一般社団法人日本カルチュアプレナー協会を立ち上げた足立さん。これまで30人以上ものカルチャープレナーにインタビューをしてこられた経験をもとに、支援のニーズについて述べられました。
「資金調達については、カルチャープレナーの皆さん共通の課題としてあると思います。ですが、清水さんや龍崎さんがお話されたように、資金以外での支援として、場の提供や大企業とのコラボといった様々な方法で、カルチャープレナーの事業を助ける形があるのではないかと感じています」
カルチャープレナーが今、感じていること

トークセッションを通じて、カルチャープレナーに対して様々なアプローチで支援ができそうだと感じたところで、後半のプログラムへ。
より具体的なトークテーマを設け、グループに分かれ、参加者同士の対話を深めていきます。
トークテーマは、参加者から提案があった「カルチャープレナー訪問」、「教育」、「大企業とのコラボ」、「企業人向け体験コンテンツ」、「資金支援」、「人材」、「10年後にカルチャープレナーがどうあったらいいか」の7つ。
どれも、これからのカルチャープレナーの活躍に欠かせないテーマばかりで、参加者の皆さんも話題が尽きない様子。50分間のセッションはどのグループも終始盛り上がり、時には笑い声も聞こえ、熱量の高い対話の時間になりました。




「カルチャープレナー同士のつながりを作っていく際には、『深める』と『広げる』という2つの方法がありそう」
「熱い想いをもったカルチャープレナーたちの存在を、メディアなどを通じて若い人にしっかり伝えていくことも、教育の観点から必要ではないか」
「他のカルチャープレナーの方のお話を伺って、今、自分なりに信じて取り組んでいる事業の『可能性』を、しっかり『確信』に変えていくことが大切だと感じました」
「10年後の姿という長期的なビジョンについて、業界を超えて色々な方の考えを共有でき、とても盛り上がりました」
など、皆さん、対話を通じて様々な気づきを得られたようです。

終盤には、京都市の松井孝治市長も駆けつけ、参加者の皆さんへメッセージを送られました。
「多才な人々が1000年以上続く京都に集い、ぬか床のように混ざり合うことで、新しい価値を創造していくことが、京都らしいまちづくりではないかと考えています。今日の交流会でも、カルチャープレナーをはじめ、参加者の皆さんが大いに混ざっていただけたらうれしいです」

「そして、カルチャープレナーの皆さんとともに、これからの京都について議論していきたいです」と語る松井市長は、挨拶の後も熱心に、参加者と交流されていました。
リアルの場だからこそ、感じられることがある
こちらは、会場の一角に設けられた「みんなに見せたい1品」コーナー。




カルチャープレナーの方が、持ち寄った自身の事業にまつわる品々が展示されています。
歴史的な書物や、伝統工芸の技術を生かした商品など、ストーリーがあって目を引く1品がずらり。フリータイム中は、この展示を会話のきっかけにして、交流を深めていく参加者の姿が見られました。


最後に参加者の皆さんの感想をお届けします!
カルチャープレナー:
「熱量を持ったカルチャープレナーの方がたくさんいらっしゃることがわかり、とても刺激になりました」
「参加者の皆さんと一緒に、未来のカルチャープレナーの姿を考えることができ、『カルチャープレナーとして活躍する』ことが、若い人たちの生き方の選択肢の一つになるようなポジションを、自分たちで作っていかなければと感じました」
支援機関:
「カルチャープレナーの方たちの生の声を聞けたことが、とても良かったです。支援者として、聞くだけで終わらせず、皆さんの想いを体現できる形を、これから作っていきたいと思います」
教育関係者:
「こうした場に、次は現場の先生たちも来てほしいと思います。文化という切り口に対して、教科書に載っている知識だけでなく、実際に今、社会で起きているこうした動きを子どもたちに教えることで、『生きた教育』ができそうだと感じています」
今回の交流会を通じて、様々なセクションの人たちが交わることで、カルチャープレナーの取組が広がっていく可能性が感じられました。今後ますます、カルチャープレナーの皆さんが京都から日本、そして世界へ、羽ばたく機運が盛り上がっていきそうです。


主催:京都市 文化市民局 文化芸術都市推進室
企画運営:株式会社よい根



