途上国から世界に通用するブランドをつくる。偏見や宗教の違いを乗り越えてビジネスを展開する「マザーハウス 」

グローバル化によって世界の距離が縮まる一方で、世界における貧富の差はますます拡大しています。各地で寄付や援助が行われていますが、表面的な支援に留まる例も多く、現地の人の生活は変わっていないという現状が浮き彫りになっています。そのような状況の中、株式会社マザーハウスは「途上国から世界に通用するブランドをつくる」という理念を掲げ、現地の人と一緒に事業を興しています。
途上国への偏見や宗教の違いを乗り越えてビジネスを展開し、数多くのイノベーションを起こしてきた当社は、内閣府「世界で活躍し『日本』を発信する日本人」(2012)、ハーバードビジネススクールクラブ「Entrepreneur of the Year Award」(2012)など数々の賞を受賞。そしてこの度、京都市の「これからの1000年を紡ぐ企業認定」第4回認定企業に選出されました。次々に生み出されるイノベーションの源泉に迫るべく、副社長の山崎大祐氏と京都三条寺町店の佐々木博國店長にお話を伺いました。
途上国の可能性を広げ、貧困をなくしたい。
── まずは、起業にいたるまでの経緯を聞かせていただけますか?
山崎さん: マザーハウスの設立は2006(平成18)年、今年で設立14年目になります。創業のきっかけは、代表の山口絵理子が、当時「世界最貧国」とされていたバングラデシュに渡ったことでした。貧しい人々の暮らしを目の当たりにし、貧困をなくすために何ができるかを考え始めたんです。そして、現地の人に話を聞くうちに、従来の支援のやり方では人々の生活を変えるのは難しいと思うようになりました。現地の人たちと一緒に事業を興したいと考えた山口は、バングラデシュの特産品である麻素材、ジュートに注目しました。日本でアルバイトをして資金を作り、真剣にものづくりをしている現地の工場を探し歩きました。失敗を重ねながらもなんとか納得のいく品質のバッグを完成させ、最初の160個を日本に持ち帰ってきました。それがマザーハウスの始まりです。


<── 今、店舗数は海外9店舗、国内28店舗に増え、海外の製造拠点もバングラデシュ、インド、ネパール、インドネシア、スリランカ、ミャンマーと6ヶ国になりました。バッグに加えて、ストールやジュエリーのラインナップも展開されていますよね。これまでを振り返ると、成長の過程にはどんなフェーズがありましたか?
山崎さん: 大きく3つに分けられると思います。最初のフェーズは、お客さまとの出会いですね。創業当時は店舗を持たずにインターネットの通販だけで販売をしていたので、思いやストーリーを伝えることができず、全然ものが売れなかったんです。次第に「お客さまの声を聞きたい」「直接自分たちの思いを伝えたい」というもどかしさが強くなり、イベントを開催するようになりました。イベントでいただいたお客さまの生の声が大きな力になり、やはり足を運んでいただける場所が必要だと、東京・入谷に家賃7万円で8坪のお店を借りました。そこから、「もっとこういうものが欲しい」「こういうところが嬉しい」というお客さまの期待に応えたいと思うようになりました。
そうして良いものを作りたいという気持ちがつのっていくものの、当時は既存の工場に発注して商品を作ってもらっていたので、自分たちが求めるクオリティのものづくりができませんでした。試作と修正を何度も依頼するのですが、工場の人たちは儲けにならないサンプル製作をやりたがらない。ならば自分たちで作るしかない、と小さなサンプルルームを立ち上げて、山口が自ら試作を繰り返しました。そこではじめて、ものを作ることと売ることが一本の線でつながったんです。この変化が、僕たちにとっての第2フェーズだったと思います。

第3フェーズは、職人とお客さまがつながったことです。2008(平成20)年にバングラデシュに自社工場が完成しました。ありがたいことに、その年に旅行会社のH.I.S.さんからツアーの話をいただいたんです。きっかけは、H.I.S.で本部長をされていたハックさんが来店されたこと。彼はバングラデシュ出身で、僕たちの取組に興味を持ってくださり、副社長を連れて現地の工場を見学しに来てくれました。すぐに話がまとまり、工場の完成からわずか3か月後にH.I.S.ソーシャルツアーデスクの法人第一号としてのツアーが始まりました。

お客さまを現地に連れていくと、工場で働く職人たちはとても喜んでくれました。「自分たちが作ったものをこういう人たちが使っているんだ」という実感が生まれ、誇りを持って仕事に取り組むようになりました。ツアーに参加されたお客さまからも「途上国への見方が変わった」「技術の高さに驚いた」などの声をいただきました。また、見学の機会ができたことで「工場をきれいにしよう」というバングラデシュでは珍しい習慣が生まれたことも、後につながる大きな変化でした。
実はこの同時期に、僕たちにとっても、ものづくりに関する重要な気づきがありました。ちょうど、3つ目の店舗が新宿の小田急百貨店にオープンしたんです。1号店、2号店は路面店だったので、来店客のほとんどはマザーハウスをよく知ってくれているファンの方でした。来店いただいた方の約9割が商品を買ってくださる状態だったのですが、百貨店の中では商品が全然売れなかった。同じフロアのほかの店にも、質の良いバッグがたくさんあったからです。百貨店で他店との競争にさらされたことで、商品力の勝負になると自分たちはまだまだ勝てないんだということを痛感しました。この経験は、マザーハウスにとって大きな転機になりました。
学校や病院を併設した、コミュニティ型の工場を作っています。
── 創業当時から社会的企業として注目を浴びてきて、今も多方面から注目され続けていますよね。その理由はどこにあると思いますか?
山崎さん: 挑戦し続けているからではないでしょうか。創業1年目に掲げた「途上国から世界に通用するブランドをつくる」という大きな理念があるので、ずいぶん長い間、「自分たちはまだなにも達成できてない」という感覚がありました。世界にはたくさんのすばらしい素材があって、頑張っている人たちがいます。僕たちの目的は、ものを売ることではなく、偏見や宗教の違いを乗り越えて現地の人々と一緒にブランドをつくっていくこと。そのために、常にチャレンジし続けてきました。お客様からも「挑戦し続けている姿に勇気をもらえる」などの言葉をかけていただくことがあり、本当に嬉しいです。
── マザーハウスの次の挑戦を教えていただけますか?
山崎さん: 現在、バングラデシュで「グリーンファクトリー」というコミュニティ型の工場を建設しています。敷地の大きさは約9000㎡、東京ドーム0.2個分です。その中に、工場のほかに学校や病院などの建物が5棟できる予定です。
── 工場に学校や病院を併設するって、なかなかないアイデアですね。
山崎さん: 現在稼働している工場は2フロア合わせて約250名が働ける規模なのですが、だんだん手狭になってきて。上の階を増設することも考えたのですが、「果たして僕らが作りたいのはビルみたいな工場だろうか?」と考えた時に、増設は違うと思いました。職人さんたちには、工場を第二の家だと思ってもらいたいんです。新しく土地を買って、自分たちらしい工場を作ろうという話になりました。現地で1年間じっくりと議論を重ね、緑が豊かで地域の人に愛される、コミュニティ型の工場の構想ができていきました。併設する病院や学校は、工場のスタッフだけでなく地域の皆さんに来ていただける場所になります。
いわゆる工場っぽい、四角い箱のような建物にはしたくなくて、デザインにもこだわりました。業界の最前線で活躍している若手建築ユニットo+hさんに設計をお願いできることになり、僕らの思い描くコミュニティ型の工場をゼロベースで考えていただきました。全社員へのヒアリングや度重なるディスカッションを経て、今年3月にプロトタイプが完成しました。豊かな自然の中にバングラデシュの伝統的な建屋の屋根がデザインされていて、見ているだけで癒されるような空間です。マザーハウスの家と呼べる場所になると思います。
このような先進的な工場の途上国での建設は、世界的に見ても前例がなく、建築の賞も目指したいと思っています。バングラデシュからコミュニティ型の工場の提案をすることには大きな意味があると思いますし、工場を建てる企業にはコミュニティに寄与する責任があるということを、広く社会に向けて発信していきたいです。
事業の目的を徹底的に深掘りするから、プロダクトにオリジナリティが出る。
── 山口代表の著書などを拝見し、マザーハウスさんの事業の進め方は独特だと感じました。まず山口さんが現地に乗り込んで、素材を探し、その場で試作品を作っていますよね。リサーチ担当が現地調査やサンプル製作、テストマーケティングをし、その後に社長が判断する、という流れが一般的だと思うのですが、今のやり方に理由はありますか?
山崎さん: 僕たちにとっては、このやり方が一番合理的なんです。形式的なリサーチをするよりも、直接現地の人に聞く方が早いので。山口と僕の2人が現地に行って、お土産物屋さんや素材の産地、工場をどんどん訪ねます。そこで山口から商品化のアイデアが出ると、僕が隣でエクセルを叩いてうちの流通に組み込める価格や品揃えを計算します。売り方が見えたらすぐにサンプル製作に入ることができるので、非常にスピーディです。
チャレンジはリスクをとらなければできませんし、合理性を考えて新しいものを生み出すのは難しいですよね。僕たちは常にゼロベースでものを考えたいと思っているので、リサーチやテストマーケティングのような前例と照らし合わせて考えるやり方はしません。そもそも、ビジネスの目的が利益を出すことではなく、世に知られていない素材やものづくりの職人さんに光を当てて、偏見や宗教の壁を超えることなので。お金はあくまでも手段としてのゴールであって、目的ではありません。今も、経済的に見ればかなり非合理的なグリーンファクトリーを建てるために、がんばって儲けているような感じです(笑)。
── 合理性だけを考えると無機質な箱のような工場ができるけど、それではマザーハウスの目的は達成できないということですね。慶應義塾大学で幸福経済学を研究されている前野先生によると、幸せは企業の経済性に直結していて、クリエイティビティも売上も社員の幸福度に大きく左右されるそうです。そう思うと、一見、非合理的に見えるマザーハウスさんの「グリーンファクトリー」も、結果的には売上や事業の拡大につながっていくのかもしれません。マザーハウスさんはこれまで、商品や作り手・顧客との関係性を含め、多くのイノベーションを生み出してこられました。その源泉はどこにあると思いますか?
山崎さん: 僕は商品のオリジナリティは開発のプロセスに宿ると思っています。もっと言うと、プロセスのさらに前段階にある目的のオリジナリティが一番大切だと考えています。でも、ほとんどの人が目的を徹底的に深堀りしないまま、事業や商品開発を始めてしまうんですよね。
マザーハウスでの例をお話しすると、2016(平成28)年にブラインドサッカー日本代表のオフィシャルサプライヤーとしてバックパックを作りました。なぜそのバッグを作ったかというと、僕たちが視覚障害の方に出会った時に、彼らの可能性を証明したいと本気で思ったからなんです。視覚障害の方が求めているのは、見えなくても感覚的に使えるバッグでした。それまでの商品開発とは全く違うニーズを掴むため、ヒアリングに9ヶ月かかりました。多くの企業は、ブラインドサッカーのバッグを作ることになっても、ここまでの期間と手間をかけないと思います。「日本代表監修」というお墨付きをもらうことが目的になっているようなケースもあるかもしれません。でも、目的がイノベーティブなものでないと、プロダクトにイノベーションを起こすのは難しいですよね。ソーシャルビジネスでは特に、目的を深堀りしたその先に、自分たちがどういうものを作るべきかの答えがある。そこで初めて、新しいものを生み出せる可能性が出てくると思っています。
ただ、その目的をプロダクトに昇華させるためにはスキルがいります。プロとして、クオリティに妥協したらだめなんです。目的を追求し、プロセスをデザインするプロデューサー的な人と、プロダクトやサービスをデザインする人、両方の力が必要ですね。グリーンファクトリーも、僕たちがコンセプトを練り、建築デザインはその道のプロであるo+hさんにお願いしています。工場ができたらスタディツアーも実施できると思いますので、ぜひいらしてください!

── 山崎さん、ありがとうございました。ここからは、京都三条寺町店店長の佐々木さんにお話をお聞きします。
各地でまちの多様性と向き合う中で、京都との相性の良さを日々感じています。
── 2017(平成29)年8月に京都三条寺町店がオープンして、丸2年が経ちますね。オープン当初から店長を務められて、いかがでしたか?
佐々木さん: これだけマザーハウスとまちとの相性がいい出店は、後にも先にもないのじゃないかと思うぐらい、はじめから良いご縁に恵まれました。京都の人は社会性や持続可能性に対する意識が非常に高くて、環境保全や伝統産業に携わる方も多いですし、どうせ買い物をするなら社会に良いことをしている企業から買いたいと思ってくださる方がたくさんいます。京都のお客さまは、マザーハウスの取組や途上国との関係、バッグを長く使う方法など、僕たちの話をすごく真剣に聞いてくださいます。店に立ってこんなに長くお客様と話すというのは、今までにない経験です。良いものを長く使おうという意識が強いんだなと思いました。
京都にお店ができる前から、京都府在住のポイントカード会員様が1000名以上いてくださったことにも、縁の深さを感じます。京都市内に物件を探す段階からSILKや京都市さんが色んなつながりを作ってくださって、代表の山口と共に京都市長とお会いする機会もいただきました。地域の方々にこんな風につながりを広げていただいたことは今までになく、マザーハウスとしても忘れられない出来事です。京都市が目指しておられる方向と僕たちの方向性が合っているんだなと度々実感しています。

── なぜ「これからの1000年を紡ぐ企業認定」にトライしようと思ってくださったのでしょうか?
佐々木さん: 認定に応募しようと思ったのは、京都市の考え方に惹かれたからです。皆さん、一個人や一企業が社会を変えるのではなく、様々な企業や団体、行政がつながって、点ではなく面で変えていくという視点をお持ちですよね。僕たちも、これまでの13年間で、自分たちだけで変えられることへの焦りのようなものを感じ始めていたタイミングでした。同じ方向を目指すほかの認定企業さんとつながり、協力し合うことが、僕たちの達成したいことへの近道になると思いました。また、東京に本店を置いているブランドなので、これをきっかけに、京都の人たちにマザーハウスのことを広く知っていただけたら嬉しいです。といっても、来店数や売上の増加を期待しているわけではなく、「認定をいただくことよりも、そこから何を実現するかが大事だよね」という話を社内でよくしています。
今、東京・名古屋・関西・福岡・台湾・香港・シンガポールにお店があるんですけど、土地によってお客さまの求めているものや好きなもの、考え方がずいぶん違います。「多様性」はマザーハウスにとって大切なキーワードの一つなので、店づくりも、それぞれの地域の多様性を大切にすることが必要だと思っています。画一的な内装やサービスで店舗を増やしても、土地の人から愛されるお店、まちを代表するお店にはなれません。まちの特性に合った商品やサービス、店構えを目指して、各地域の限定商品を作り、イベントにも工夫をしています。京都三条寺町店でも、第1回認定企業の坂ノ途中さん、DariKさんとのトークイベントなどを実施してきました。今後は、地域の学校に出向いて世界の多様性や力強さについてお話しする機会を増やしていきたいと思っています。


── 佐々木さんは3年ほど前に入社されたんですよね。前職はどんなお仕事をされていたのですか?
佐々木さん: 証券会社で7年半営業をしていました。株や債券をお客さまに販売する仕事で、たくさんの資産を預かっていました。。為替は24時間絶えず変動していますし、お客さまに怒られることや営業目標のプレッシャーもありましたね。でも、待遇も良かったし、刺激的でおもしろい仕事でした。
証券会社に入社したのが2009(平成21)年4月、リーマンショックの翌年でした。当時7,000円だった日経平均株価は、退職時には20,000円台になっていました。会社も順調に成長していて、でも、その割にはお客さまの資産が増えていなかったんです。そこに疑問を感じました。基本的に、会社にとって利益の大きい商品は、お客さまの利益にならないものが多いんです。お客さまに喜んでもらえる営業をしていても、社内では評価されにくいという仕組みが見えてきました。本当にこれでいいのかと悩むようになり、自分がどういう人間なのか、どういう働き方をしたら幸せを感じられるのか、2年間もやもやと考え続けました。その結果、やっぱり自分が提供するサービスを通じてお客さまに幸せになってほしい、「三方良し」を目指す組織で働きたい、という気持ちが強くなって。そんな時期に、以前から知っていた代表の山口の本を読み返して、商品の作り方・売り方・人との接し方、どこを見ても自分のやりたいことを体現している会社だと感じました。


── 最後に、佐々木さんにとってマザーハウスはどんな存在ですか?
佐々木さん: 大学生の頃、オーケストラサークルに所属してクラリネットを吹いていました。たくさんの人が演奏を聴いて喜んでくれるのが嬉しくて、長時間の練習も全く苦にならず、とにかく良い演奏をすること、楽器の腕が上達することに夢中でした。仕事もそういう風にできたらいいなとずっと思っていたのですが、マザーハウスでの仕事には、まさにその時のように熱中しています。会社のビジョンが自分の目指すところに近いこともあり、とても充実した日々を過ごしています。スタッフも個性的なメンバーがそろっていますので、ぜひお店に遊びに来てください。

── ありがとうございました。また佐々木さんやスタッフの方に会いに、お店に伺います!
取材・文:山中 はるな / 柴田 明(SILK)
■企業情報
株式会社マザーハウス
〒110-0016 東京都台東区台東2-27-3 NSKビル2F
京都三条寺町店:〒604-8036 京都府京都市中京区 三条通寺町東入 石橋町4 さんてらすびる1・2F
TEL|03-5846-881
URL|https://www.mother-house.jp/
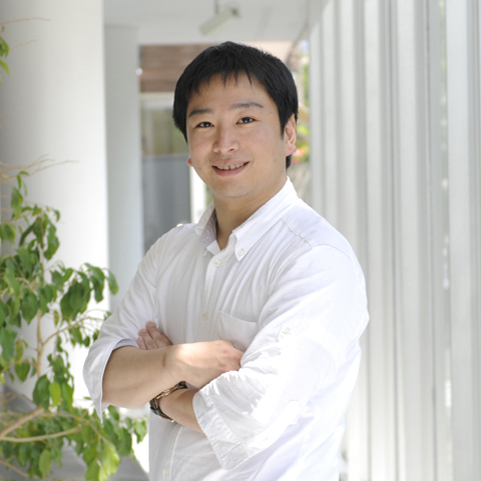
山崎 大祐(やまざき だいすけ)
株式会社マザーハウス 代表取締役副社長。 1980年東京生まれ。慶應義塾大学総合政策学部卒業。 大学在学中にベトナムでストリートチルドレンのドキュメンタリーを撮影したことをきっかけに、途上国の貧困・開発問題に興味を持つ。 2003年、ゴールドマン・サックス証券に入社。エコノミストとして、日本およびアジア経済の分析・調査・研究や各投資家への金融商品の提案を行う。 2007年3月、同社を退社。大学時代のゼミの1年後輩だった山口絵理子が始めたマザーハウスの経営への参画を決意し、同年7月に副社長に就任。マーケティング・生産の両サイドを管理する。

