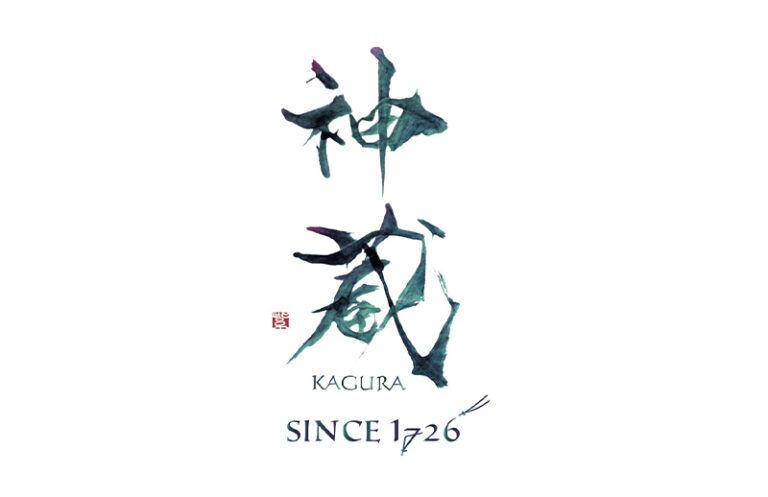-
経営理念
水産資源を守り、日本の食文化を守る
うね乃では、水産資源を守り、日本の食文化を守るため、原材料の廃棄の抑制、フードロス削減を目標に掲げています。
業界をめぐる深刻な問題として、原材料となる水産資源の減少や枯渇化が進んでいる事が挙げられます。水産庁の「数字で理解する水産業」によると、日本の漁業における生産量は1980年代ごろから減少しています。1984年のピーク時は1282万トンだったのが、2018年には442万トンです。
(引用:水産庁|数字で理解する水産業)
生産量が半分以下にまで落ち込んでいる原因は、過剰漁獲や資源状態の悪さ、違法漁業による漁獲量の増加、海洋温暖化による生態系変化が考えられます。
古くからのうね乃の事業を守り、漁業関係者、地方生産者の生活を守り、従業員の生活を守るため、状況の改善に少しでも貢献し水産資源の保全活動につながる経営活動を行いたいと考えています。 -
経営理念に基づいて、具体的に取り組んでいること
各地方から調達した生産物(原材料)をくまなく使い切る
限られた資源(食材)を無駄なく大切に活用するため、各地方から調達した生産物(原材料)をくまなく使い切る努力を行っています。
例えば製造工場からはたくさんのだしガラが出ます。だしガラはまだまだ旨味を有していますが、それらをそのまま捨ててしまえば産業廃棄物としてゴミになってしまいます。
うね乃ではだしガラを選別して、最新技術を活用してだしガラを乾燥させ、昆布の佃煮やふりかけの原料としてUPCYCLEし、新たな製品を製造しています。また、かつお節やまぐろ節などのだしガラを乾燥させたものを粉末にし、ペットフードの開発を行っています。その他にも、乾燥させただしガラを滋賀県にある自社農園の有機肥料として畑に散布し、その農園で育った野菜を自社製品の原材料として使用しています。 -
今後のビジョンや展望など
出汁文化を日常品として、オリジナルのままその時代に合うものに
ここ数年、だしブームの様な現象が起こっておりますが、だし専門店以外の方が参入されることも多く、日本人が育んで来た技法や味にとどまらず出汁の存在そのものまでもが変化している様に見えます。時代と共に変化し、テクノロジーの後押しもあり変わっていく姿は世の常とも言えますが、鰹節は数千年前より我々の先駆者の努力のもと伝承してきた正に奇跡の逸品と言っても過言ではありません。出汁文化を日常品として、いかにオリジナルのままその時代に合うものにするのかが、うね乃の役割と自負致しております。
「簡便性高い本物」をスローガンに和食以外の食文化にも使える様な製品やレシピ開発は出汁のブレンダーとしての強みと考えます。
昨今の様な海洋資源の枯渇化が進む時代には海と山の共存性を上げた出汁の提案や原料模索を行いオリジナルのまま次世代にバトンを渡せるよう自然界と向き合っております。
製法につきましても、約100年前の削り器を使用することで、古式製法ならではの滋味深い出汁作りに繋がっております。
それに伴う職人技をレベルアップさせるとも共に、その門下生の育成にも幅広い視点で募っております。数百年、千年先にも人間力が一番魅力とされる企業を目指しております。
-
取り組みにより、どのような社会的インパクトを起こしてきましたか
食品ロスを無くす取り組みに共感した企業との協力関係
食材の二次活用や技術力向上の方法を自社だけのものにせず取り組み内容を発信しています。その結果、食品ロスを無くす取り組みを評価いただいた事業者様との新規取引が始まったり、だしがらをペットフードとして活用いただける事業者様や、肥料として活用いただける農家様との関係が生まれたり、取り組みを見学するツアーを企画いただける旅行者様との関係が生まれたりと、取り組みに共感した企業様との協力関係を築くことができています。
-
今後のビジョンや展望により、どのような社会的インパクトが期待できますか
限られた資源をより有効に、無駄なく使う
海洋資源の枯渇化が叫ばれる昨今、これまでと同様の大量生産大量消費を続ける事はできません。技術力の向上、新たな製品の開発により、限られた資源をより有効に、無駄なく使う企業努力を行います。その姿勢を生産者や消費者に伝える事で、近い将来、遠い将来の食を守る事を、全ての人が意識する社会になると自負しています。
-
従業員・顧客・取引先への配慮
お互いの顔をみて、状況を理解しあってお取引を行っています
ステークホルダーとの対話
主要原材料の鰹をはじめとする魚の節や昆布、その他野菜や調味料などの生産者(仕入先業者さま)と深く密接につながり、お互いの顔をみて、状況を理解しあってお取引を行っています。それにより、一方が利益を得るような過度な価格交渉や、納期や納品量の無理な要求が無い関係を築くことが出来ます。販売先様にもうね乃の製造スタイルや考え方を理解いただいているため、一方的で無理な要求はお互いにする事を避けることができています。また、うね乃が橋渡しになり、生産者と販売者、消費者がお互いに意識しあえる関係づくりに努めています。
差別の禁止
働く社員それぞれのアイデンティティを大切に、尊重して働いてもらえるよう徹底しています。特定の理由を基に差別やハラスメントが起きない様、相互監視の仕組み作りを進めています。
労働安全衛生
食品製造を行う工場では、同一業種では先駆けて、2020年に水産HACCP認定を取得し、徹底した衛生管理を行っています。工場内で働くスタッフだけでなく、会社で働く全てのスタッフが自主的に衛生管理を意識する環境があります。衛生管理を意識する事は安全な労働環境にもつながり、意識の向上により安全で衛生的な労働環境がスタッフの力で形作られています。
人材育成
全社員を対象に、外部講師を招いて自己啓発の研修を実施し、若年層からベテラン層までが学ぶ機会をつくっています。 -
地域社会への配慮
みんなで子どもや若者を育み支えていく『ALLOCARING(アロケアリング)』
地域への参画
地域の保育園、幼稚園、小学校からご依頼をいただき、食育に取り組んでいます。こちらから出向いたり、うね乃にお越しいただいたり、色々な方法で実施しています。工場の見学や色々な種類の削り節を使ったおだしの飲み比べ、ふしの状態の鰹節をかんなで削ってかつお節にする削り体験をします。"お出汁"を通じて、触れることが少なくなってしまった日本の食文化に、実際に触れて体験してもらえる空間を作っています。
その他
母親や実親ではない人々が子育てをすることALLOMOTHERING(アロマザリング)、ALLOCARING(アロケアリング)といいます。うね乃では、さまざまな課題を自分ごととして 受け止め、繋がり包み込み、人類という大きなひとつの家族として みんなで子どもや若者を育み支えていく『ALLOCARING アロケアリング』が 可能な社会を目指していきます。人生のなかでの大きな意義となる『働く』ということ。 たくさんの時間を費やす働く場所は、若者にとっていろいろな人と 有機的に繋がる場となります。その実践の一つの形として、ALLOUNENO(アロウネノ)は、 アロケアリングの考えから、 若者たちをみんなで育み支えていく居場所づくりの実践のため、2021年12月につくられました。多様な雇用の創出、人同士のつながりの創出を行っています。 -
環境(未来の社会)への配慮
だしがらを乾燥させて原材料として活用し、フードロスを削減
廃棄物等の適切な管理、再利用、再資源化
うね乃には14種類の液体だしつゆとジュレ製品があり、これらを製造するためのだしを取るため、かつおやまぐろ等の削り節と昆布を大量に使用します。1カ月で平均すると、削り節で85.0kg、昆布で4.5kg以上のだしがらが発生します。
これらをそのまま廃棄対象とした場合、その全てがフードロスとなりますが、うね乃ではスチームコンベクションを活用してそれらを乾燥させ、だしがらを原材料として二次利用した製品を開発、製造、販売しています。
だしがらを乾燥させて原材料として活用する事によりゴミを削減し、環境へ配慮した経営を実践しています。
文化の継承・発展
京都府下の社寺仏閣とのつながりがあり、祭儀に参列しています。また、ご奉仕として社員を派遣しています。