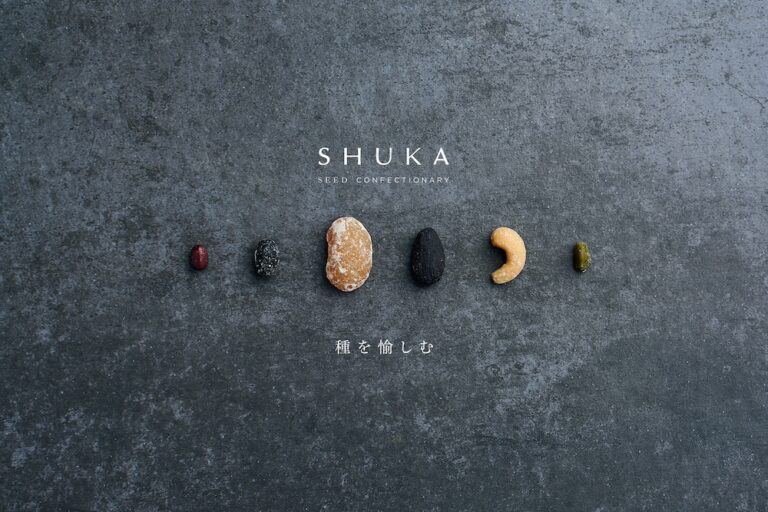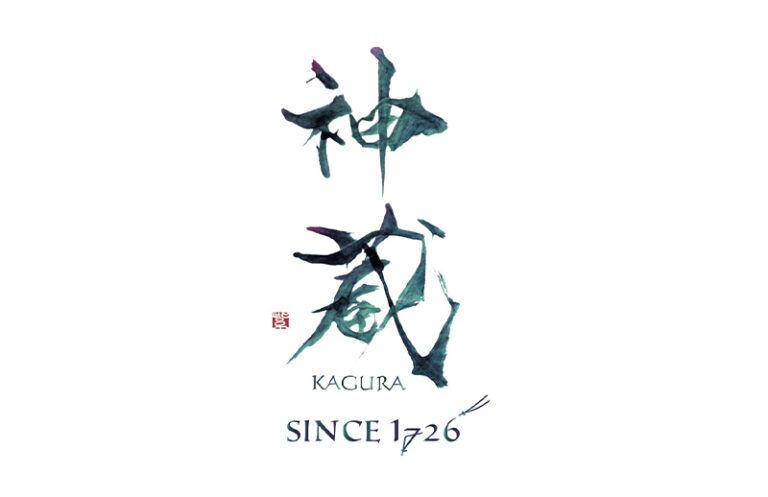-
経営理念
自然と人が調和した美しい世界を伝え残す
「自然と人が調和した美しい世界を伝え残す」
弊社は京都で1926年創業の甘納豆専門店である。甘納豆は年々廃業が続いている。現代表である4代目は、京都大学大学院で微生物を研究し、生き物に関心が高かった。甘納豆は日本の食文化としてもちろん重要であるが、それ以上の意味を考え続けた。
甘納豆は、豆の色や形を残す菓子である。この点に4代目は、自然を尊ぶ心があると感じた。自然の恵みに、節度を持って人の手を以って菓子とする。菓子の名前などよりも、この価値観こそ、今後も残していく価値のあるものだと考えた。
自然と人間社会との調和が求められている。どれだけハード面において環境技術が発達したとしても、それを扱う人に、自然を尊ぶ心がなければ、その技術は本来の機能を発揮しない。
ソフト面において、この日本で育まれてきた精神性こそが世界に必要なものであると考え、その先にある、自然と人が調和した、美しい世界を伝え残すことを理念に据えた。 -
経営理念に基づいて、具体的に取り組んでいること
自然電力、アップサイクル、在来種の継承
・従来の石油由来の熱源から、設備を一新し、自然電力で菓子作りをしている。
・従来の甘納豆作りにおいて廃棄されることが多かった副産物であるシロップをアップサイクルして、新たに独自の植物性ジェラートを開発した。
・地元京都の生産者と共同で、在来種である瑞穂大納言小豆の継承に貢献している。 -
今後のビジョンや展望など
古くて新しい種菓子ブランド「SHUKA/種菓」
前述の経営理念を実行るために「種を愉しむ」をコンセプトに、2022年、大きなリブランディングを実行し、古くて新しい種菓子ブランド「SHUKA/種菓」を立ち上げた。
自然と人との接点は、一粒の種を植えること(つまり農業)から始まる。世界三大穀物(米、小麦、とうもろこし)は全て"種"であり、世界中の人々は種を食べて生きている。種は、水や空気と同じく、生きるためになくてはならない重要なものである。
種には様々な課題がある。遺伝子組み換えや、ある品種が市場を占有することによるモノカルチャー化(生物多様性の喪失)。現在種は買うものになっているが、日本においてはその自給率は10%以下であり、海外産の種に依存していること、などである。
ただ、これらの課題よりも大前提として、しかし、種を食べているという実感を持っている人は少なく、認識されていないこと、が最も課題であると考えた。
そこで当社では、種を食べるという体験を通して、種を食べる愉しみを通して、多くの人に種と関わる接点を持つことが役割であると考えた。
現在もオリジナルの植物性ジェラートを開発し、日本だけでなく訪日外国人に対してもアプローチをしている。
今後さらに、種を育てる愉しみを提供したいと考えている。
-
取り組みにより、どのような社会的インパクトを起こしてきましたか
甘納豆のイメージ転換や認知向上
リブランドした「SHUKA/種菓」では京都のクラフトチョコレートベンチャー「Dari K」とコラボした「加加阿甘納豆」をはじめ、ピスタチオやカシューナッツに合う糖を掛けあわせた新商品を発表。従来の甘納豆の技術を用いて、海外や若い世代にも受け入れられやすい、新たな価値を持った商品を生み出した。
クラウドファンディングを実施した際には目標を超えた金額が集まり、甘納豆のイメージ転換や認知向上につながった。 -
今後のビジョンや展望により、どのような社会的インパクトが期待できますか
自分が食べるものを自分で育てる、という体験
自分が食べるものを自分で育てた経験がある人は少ない。自分が食べるものを自分で育てる、という体験からは多くのことが学べる。例えば、食べ物の旬はいつか、無農薬とはどういうことか、どんな花が咲くのか(そしてどんな風に種ができるのか)、食べ物のありがたみ、などである。
最初に育てる作物として適しているのは豆である。なぜなら、豆は育てやすいからである。窒素は肥料として重要であるが、豆科は空気中の窒素を栄養源とすることができる特殊な性質を持っている。むしろ、豆を植えた方が土が豊かになる。場所もとらずマンションのベランダでも十分である。豆で成功体験を積めば、そこから他の野菜を植えてみるのも良いし、同じ豆を継いでも良い。
これらの体験は自然な形で、自然を尊ぶ心を育み、フードロスの削減やひいては食料自給率の上昇にも貢献できる。
豆を植える人が増えるために重要なものは土であると考える。なぜなら自身の経験として、そもそも都会の家に土がないからである。そのため現在、コンポストとのコラボレーションを想定している。なぜなら、土(肥料)から自分で作れば、何か植えたくなるはずである。そこで、まず豆(小豆を想定)を植えてもらうことを推奨する。小豆は日本において認知度はほぼ100%あり、和菓子の基本素材としても重要である。
小豆が収穫できれば、自然と食べてみたくなり、その調理過程において、和菓子への興味や、その価値の向上にも貢献できる取り組みになると考える。 -
従業員・顧客・取引先への配慮
植物性ジェラートを開発し、ヴィーガンの方に食の選択肢を提供
【ステークホルダーとの対話】
畑へ足を運び、素材を吟味・研究し生産者の方々と共に、人も地球も喜ぶ菓子づくりに努めており、種や和三盆は、在来品種や有機栽培・無農薬栽培を選んでいる。
【差別の禁止】
全員で6人の体制の中、20代~70代が協業している。
【その他】
本場イタリアンジェラートの配合理論を学び、牛乳の代わりに"種"を使った独自配合から生み出す代替品の枠を超えた新たな植物性ジェラートを開発し、乳製品にアレルギーを持つ人をはじめ、ヴィーガンにも食の選択肢を提供している。 -
地域社会への配慮
在来種である瑞穂大納言の無農薬契約栽培
【地産地消の推進】
京丹波町瑞穂地区の在来種である瑞穂大納言の無農薬契約栽培に取り組んでいる。また、砂糖漬けやジェラートに名前をそのまま入れることにより、認知向上、ブランド向上にも貢献している。 -
環境(未来の社会)への配慮
従来の石油から、自然電力への切り替え
【温暖化対策・2050年CO2排出量正味ゼロへの取組】
熱源を、従来の石油から設備投資をし、自然電力に切り替えた。
【廃棄物等の適正な管理、再利用、再資源化】
甘納豆は砂糖漬けという古来の食品保存技術で作られ、副産物としてシロップが発生するが、これは加熱で風味が変わっていってしまうため何度も使うことはできず廃棄することもあった。このシロップをアップサイクルし、ジェラートの約20%相当に使うことで、種のエキス分が加わりさらに"種"を感じるジェラートとなっている。
【文化の継承・発展】
日本の食文化である甘納豆を、従来接点のなかった若い世代や海外の方に伝えている。