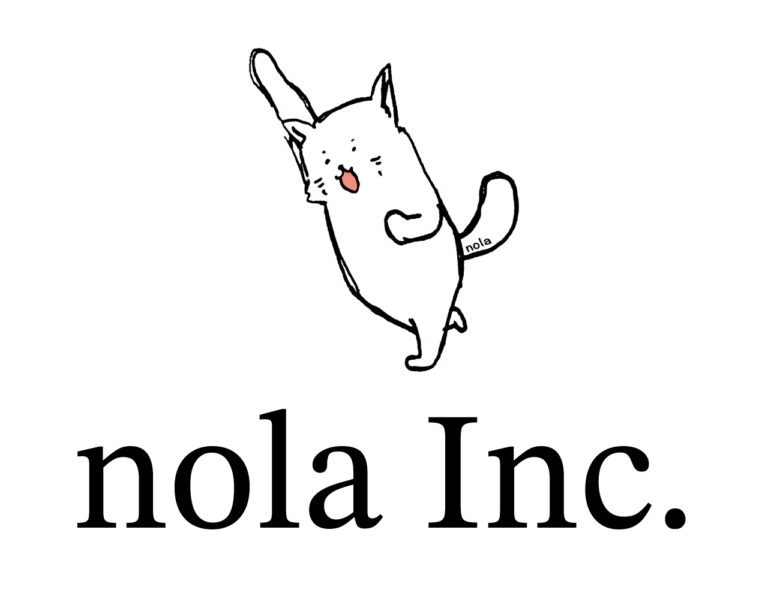2024年度認定
-
経営理念
「小さくても大きな仕事を」「自分らしく生きる」
弊社は京都に小さなデザイン会社をかまえ、社員数名と「小さくても大きな仕事を」と「自分らしく生きる」をモットーに日々お仕事をしています。
弊社は会社規模としては小さい会社ですが、多くのフリーランスとパートナー契約をしており、その多くは主婦であったり、介護をしているとか病気といった、なんらかの理由で企業に就職ができない方です。そういった方は、固定時間で働くことは難しいですが、時間に融通がきけば、スキルは高い方が多いので、問題なく働くことができます。
弊社がプロジェクトマネージャーとなり、そういった方々とチームを作ることで、さまざまな仕事をこなすことができます。
このスタイルは、弊社代表である瀬戸の実家が宮大工だったことから、その宮大工の仕事スタイルを踏襲しています。
一人一人は小さくでも、集まることで大きな仕事ができる。そして、自分が得意を持っていることで、どんなスタイルでも働くことができる、このスタイルを「自分らしく生きる」をモットーにできる理由としています。 -
経営理念に基づいて、具体的に取り組んでいること
普通の雇用形態でなくても人材を確保できる仕組みを提供しています
最初のきっかけは、ブラックと言われている広告デザイナーとして活躍する中で、このような働き方では子供を育てるのは難しいと感じたことでした。ブラックな働き方というのは、具体的には勤務時間の長時間化が一番かと思います。お客様の返答や指示が、お客様の営業時間後になることが多く、そうなると、そうなると必然的に残業や深夜勤務が当たり前になっていました。
ブラックになる原因は、お客様との関わり方や契約を工夫することで、もっと無理なく働けると感じ、そうしたお客様と仕事ができるよう、自分で選べるよう起業をしました。
クリエイター業は営業時間があってないようなものですが、逆にそれを活かすと、普通の時間に働きにくい人でも働ける状況が作れることがわかりました。
働き方を工夫することができると、さまざまな困難を抱え、現状まともに働くことができない人でも、優れたスキルを持っている人が結構多くいることがわかりました。
スキルがあるのに、通常の雇用形態だと働くことができない。少しの工夫で、優れた人材を雇用できる。
今、人材不足で悩んでいる企業の方に、このことを知ってもらいたいと思いました。
普通の雇用形態だと、人の管理がしやすいのだと思いますが、普通の雇用形態で働くことができない方の人の管理を弊社で行うことで、普通の雇用形態でなくても人材を確保できる仕組みを提供しています。具体的な仕組みとしては、働く総時間は決まっていますが、勤務時間を固定化しないことで、その方が働きやすい時間に作業をすればいいようにしています。また、コミュニケーションをチャットツールにすることで、リモートが可能ですし、また、今すぐ見なくても、双方が都合の良い時間にやりとりができるということも利点になっています。さらに、制作したもののデータ管理を全てクラウド管理にすることで、どこにいても全員が同じ場所に格納でき、どこでも必要な情報を引っ張ったり、納品したりが可能になっています。
弊社は、広告デザインの分野で、広告デザインという部署をや人材を持っていない企業に対し、外部のインハウスデザイナーとして入り込み、人の管理とデザインの監修を行なっています。
1企業が広告デザインをするために1人の人材を雇用することはとても大変です。まして、普通の雇用形態で勤務ができない人を採用し、活かすことは無理でしょう。
そこで弊社が入り込むことで、その部分を補うことをしています。
また、そうした優れたクリエイターを輩出するために、さまざまな障害を持った方の就労移行支援をしているNPO法人とタッグを組んで、クリエイターの育成も行なっています。 -
今後のビジョンや展望など
弊社(クリエイター)・地域(障害と持った方)・企業(お客様や当プロジェクトに関わる企業)の3方よしが実現できるプロジェクト
その活動の一環で、現在進めているのが「ハガキで日本を変える★プロジェクト」です。
弊社(クリエイター)・地域(障害と持った方)・企業(お客様や当プロジェクトに関わる企業)の3方よしが実現できるプロジェクトになっています。
きっかけは、障害を持った方の就労移行支援をしているNPO法人と行っているクリエイターの育成で、そこで出会った方たちはとてもイラストを描くのが上手で、アール・ブリュットと言えるくらい、すばらしいものでした。
しかし、就労移行支援施設で就職を目指す場合、行く先は広告デザイン会社などになりますが、そういったところはクライアントワークになるため、この方達のアーティスティックなデザイン性が生かされるような仕事であることは難しく、せっかくのイラストの技術が生かされていない状況でした。
この優れた才能を、生かすことはできないかと考えている中で、ハガキの制作を思いつきました。
弊社もデザイン会社ですが、実はこれまで一度も営業活動をしたことがありませんでした。どうやってお仕事をいただいていたかというと、私はスタッフが、交流会だったり何かのイベントに行った時などに名刺交換をした際、絵はがきでお礼を書いて送ったり、年度末のお礼状などを絵はがきにして送っており、そうした活動により覚えていたくださったお客様からのつながりでお仕事をいただいていました。
こうしたハガキでの活動は、ただ営業活動をするのより、実はもっと深く印象に残り、忘れられない存在に慣れていることに気づき、また、その絵はがきの絵柄を先ほどの才能ある方に描いてもらったイラストを使うことで、印象にも残っていたことが生きていることに気がつきました。
そこで、こうした絵はがきでのつながりによる活動をもっと多くの中小企業に知ってもらい、絵はがきを活用してもらうことで、企業間同士の繋がりも強くなるし、また、先の就労移行支援のクリエイターの方たちも仕事を生み出すことにもなると感じました。
これにより、最初に書いた「弊社(クリエイター)・地域(障害と持った方)・企業(お客様や当プロジェクトに関わる企業)の3方よしが実現できるプロジェクト」として、ハガキプロジェクトを進めようとしています。
さらに、社会に役立つものにするため、昨今利用が減ってきていると懸念されている地域企業の印刷会社さんやハンコ屋さんも巻き込み、地域企業を盛り上げる活動にも繋げたいと思っています。 -
取り組みにより、どのような社会的インパクトを起こしてきましたか
障害を持った方の雇用の創出にも力を入れています
現在、弊社では実際に3つの企業に入り込んでいます。
その1つでは、京都御苑を管理している国民公園協会様に入らせていただき、WEBサイトの管理や植生作業の報告業務などを担っています。
そういった業務はスキルがとても多岐に渡り、その多岐にわたるスキルを1人の人が持つようなことは難しいのですが、弊社のメンバーが入ることでその多岐にわたるスキルの業務を行うことができます。
1つの業務に1人が担当するのではなく、データやスキルを共有することで、複数のメンバーが関わり、どのメンバーに緊急なことがあっても誰かが対応できる仕組みにしています。
そうすることで、1企業が複数の人を雇用しなくても、多岐にわたる業務を任せていただくことが可能になっています。
また、地域の就労移行支援施設と協力し、障害を持った方の雇用の創出にも力を入れています。 -
今後のビジョンや展望により、どのような社会的インパクトが期待できますか
企業に入り込むだけでなく、弊社自身で仕事を生み出すようなことも進めています
今後は、こうした取り組みを多くの企業に理解をしてもらい、採用していただける先を増やしていこうと思っています。同時に、企業に入り込むだけでなく、弊社自身で仕事を生み出すようなことも進めています。そうすることで、多くの優れたクリエイターが自分のスキルを活かすことができ、一人でも多くのさまざまな状況を抱えた就労者を増やしていきます。
-
従業員・顧客・取引先への配慮
定期的に面談をするなどして、安心して仕事を発注していただけるようにしています
まず、顧客や取引先に向けては、多様な要望に対応できる人材の確保を行っています。特に、障害者の活躍に力を入れていて、障害を持った方の特性を把握したり、それを企業側に周知してもらいやすくしたり、また定期的に面談をするなどして、安心して仕事を発注していただけるようにしています。
また、従業員や外部パートナーに関しては、それぞれの特性や状況を把握し、その方にあった仕事の依頼をしたり、スケジューリング等、取引先様と話し合って調整ができるようにしています。
そして、取引先に頼るだけでなく、自社での仕事を生み出すことをしていくため、新たな取り組みとして、絵はがきの販売をスタートしました。 -
地域社会への配慮
障害者雇用に関するサポートなども行っています
地産地消では、絵はがきを印刷する紙や印刷を地元企業に発注するなど、積極的に地元企業を活用しています。
地域への参画では、地域の就労移行支援の利用者さんを積極的に業務に活用したり、育成の一環でセミナーを行ったりしています。
また、就労移行支援施設の方を活用する際、企業や地域に理解を持っていただくために、障害者雇用に関するサポートなども行っています。 -
環境(未来の社会)への配慮
地元の子供食堂に家で採れた野菜を提供
廃棄物等の適正な管理、再利用、再資源化では、絵はがきの紙を、地元の印刷会社の端材を使用するなど、サスティナブルに配慮しています。
地域ぐるみでの子育て支援では、地元の子供食堂に家で採れた野菜の提供などを行っています。