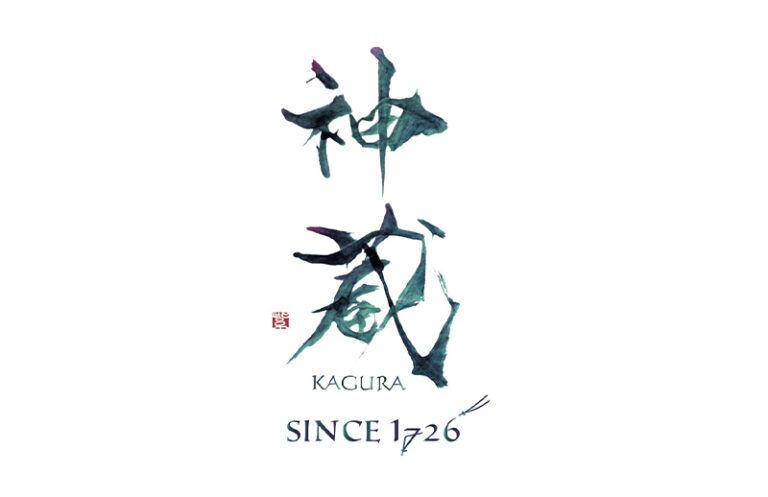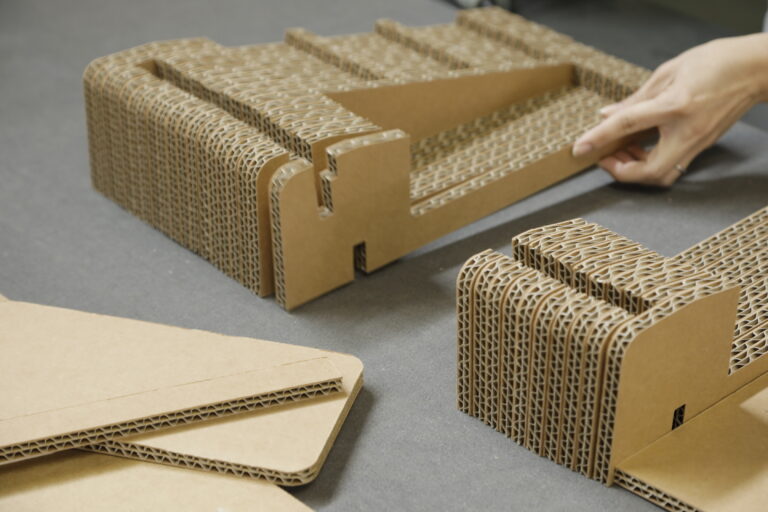2024年度認定
-
経営理念
キットヲキニメス
弊社は「キットヲキニメス」を経営理念に掲げています。この言葉は、弊社の3代目が看板商品である「栗赤飯」を京都で初めて売り出した際に、打ち出した広告のキャッチコピーです。既存の商品にせよ、新しい商品にせよ、お客様の目線に立ってお客様が「お気に召す商品」を世に送りだす。そして、自分の仕事に誇りを持つこと。そんな弊社の精神を体現した言葉です。
-
経営理念に基づいて、具体的に取り組んでいること
マンガやアニメなど新しい文化や価値観と交わる商品の開発
1,マンガやアニメなど新しい文化や価値観と交わる商品の開発
弊社が手掛ける、お餅やお赤飯、和菓子といった商材は、ここ数年市場規模が横ばい傾向であり主な顧客層の高齢化が進んでおり、社内の分析においても40代以上かつリピーターの顧客が全体の大きな部分を占めていました。また、核家族の進行やコンビニスイーツの出現など生活スタイルの変化も重なり、主に30代以下の年齢層にとって「和菓子屋」という存在が縁遠いものに変化しており、この現状を鑑み若年層に「和菓子」、そして「和菓子屋」という存在をより身近に感じてもらうため、マンガやアニメといった若年層に馴染み深い異業種コンテンツとのコラボ商品の開発を2017年頃から積極化しました。保守的かつ権威主義な傾向が強い京都の和菓子業界にあって稀有な事例となり、以後も商品開発やコラボレーション企画の依頼が舞い込むようになりました。
2,冷凍食品および冷凍対応商品の開発
弊社は京都の食文化をより多くの方に認知いただき、楽しんで頂くために、同じく京都の地で創業された冷凍食品会社「株式会社チャントミール」との共同開発により、電子レンジの加熱のみで喫食ができる、弊社の餅を使用した「白味噌雑煮」を開発・販売いたしました。COVID-19のパンデミックを受け、開発に着手した本商品ですが、冷凍商品であるという強みを活かし、全国どこででも京都の味を楽しめる商品としてご好評を頂いています。本商品の発売まで「京都の白味噌のお雑煮」を手軽に食べられる商品そのものが存在せず賞味期限も非常に長いことから、主に一人暮らし層での需要が高く、京都の食文化をより身近に感じることができるようになりました。また、弊社においてもECの一般化に伴いフードロスや顧客利便性の観点から「冷凍対応商品の開発」も積極化しています。
-
今後のビジョンや展望など
和菓子という食文化をより楽しく、生活に根付いたものとして次世代に継承する
弊社は経営理念をより深化、実践するために「ココロ豊かに、チカラ身に充つ社会を実現する」ことをビジョンに掲げ以下のことに取り組んでいます。
1,和菓子への理解を深め、楽しむための体験型イベントの開催
和菓子やそれらを伴う行事に対しての意識が薄れつつあるなか、それら楽しみながら理解を深められるような体験型イベント企画し、国内外に広くPRし、京都の町衆に受け継がれてきた文化風習を啓蒙し次世代に繋げるための取り組みを行います。
2,従業員それぞれが成長を実感できる人事評価制度の構築
和菓子業界においてもっとも重要な課題が後継者不足です。とくに職人の減少は、手作りを基本とする伝統的な京都のお菓子にとって死活問題です。弊社では誰もが仕事にやりがいと達成感を得られる環境を提供するために、従業員それぞれがやりがいと成長を実感できる人事評価制度の構築と施行を目指します。
3,より根源的な和菓子体験の提供
私たちは和菓子という食文化をより楽しく、生活に根付いたものとして次世代に継承することによって、「心豊かな生活」と「活力に充ちた」社会の実現を目指しています。単にお餅や赤飯、和菓子を提供する企業であるだけでは、この目標は達成できません。「和菓子屋で和菓子を買い、文化的な体験をする、先人の祈りや光景を追体験する。」弊社ではこの一連の流れを事業活動を通じてデザインしていきたいと考えています。 -
取り組みにより、どのような社会的インパクトを起こしてきましたか
若年層や普段和菓子と馴染みの無い顧客層の来店が見られました
第一に、「マンガやアニメとのコラボレーションによる商品開発」においては、当初の目的であった若年層や普段和菓子と馴染みの無い顧客層の来店が見られました。これによって、まず「和菓子屋に来店する」という行為そのもののハードルを下げる事に成功し、また「マンガやアニメ」という日本が世界に誇る文化の上に「和菓子」という存在を加えることで、互いの顧客の交流や新たな市場を生み出す事にもつながりました。
第二に、「冷凍商品や冷凍対応商品の開発」においては、フードロスの削減や孤食層への健康的かつ文化的な食品の提供。食文化を全国に認知することができました。
第三に、これらの取り組みは新たな顧客層を開拓し需要拡大を目指す取り組みであることから、国産材料の需要喚起にも繋がります。弊社が取り扱う原材料の主な取引先は、国内の農産地や卸問屋であり、これら新たな取り組みによる新規需要の形成は国内および地域経済の活性につながります。 -
今後のビジョンや展望により、どのような社会的インパクトが期待できますか
「ココロ豊かに、チカラ身に充つ社会」
弊社は「ココロ豊かに、チカラ身に充つ社会」というビジョンを掲げています。本ビジョンは、物質的な豊かさだけでなく、文化や伝統に裏打ちされた暮らしを営むことによって、心の豊かさを増幅させ、これによって笑顔や活気に溢れる町『京都』を、そして日本を元気にすることを最終目標とするものです。
弊社ではこのビジョンの実現に向けて、様々な取り組みを展開しています。これらの施作は「日本固有の食文化である和菓子を次世代により良い形で継承する」「より良い和菓子文化の担い手を育成する」「和菓子という食文化をより多くの人に楽しんでもらえるものとする」為の取り組みであり、この3目標を達成することにより、「和菓子」そのものの持続性を向上させ「和菓子が紐づいた京都の文化風習に根付いた体験」を通じて、さきほどのビジョンを着実に実現していきたいと考えています。 -
従業員・顧客・取引先への配慮
定期的な産地訪問を行っています
1,ステークホルダーとの対話
・主要原材料である、米や小豆などについて定期的な産地訪問を行い、育成状況や生産状況の把握、市場動向の共有など、情報交換を密におこない、関係性を構築することで安定供給できる体制を構築しています。
・顧客に対してはSNSを主軸とした広報活動を行い、自社活動を発信するとともに、顧客の意見などを取り入れながら事業活動を行っています。
2,差別の禁止
・社内でSDGs宣言を策定し、従業員に認知を広げるなど、性別、年齢、障がい、国籍、出自などによる差別や各種ハラスメントを防ぐ体制が整備し、社内で差別や人権侵害がないよう取り組んでいます。 -
地域社会への配慮
京都府立植物園や地域企業の株式会社Casieとのコラボ
1,地域への参画
・中学生を対象にしたスポーツ団体にコーチとして、経験のある社員を派遣、当該活動への参加に対しては早退や休みを認めています。
・地域活動に参加する社員に対しては早退や休みを認めています。
2、その他
・弊社三代目が考案し、京都で初めて売り出した「栗赤飯」の100周年の記念事業を実施。企画の一つとして、京都府立植物園や地域企業の株式会社Casieとコラボを行いました。異なる分野や業種においても重なる部分を見つけ、地域全体の活性化を図っています。 -
環境(未来の社会)への配慮
残渣物や規格外品を活用した商品を開発
1,廃棄物等の適正な管理、再利用、再資源化
・食品ロス削減のため、毎日終業時に数量を確認し記録に残し、削減のための目安としています。
・製造工程で発生する、残渣物や規格外品を活用した商品を開発し販売しています。
2,情報開示
・理念、事業内容、福利厚生等のほか、環境、社会貢献に関する情報を発信しています。