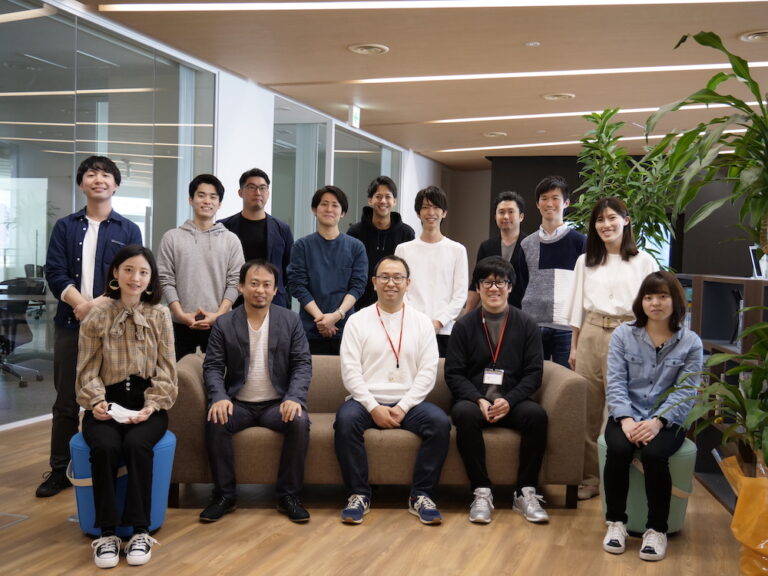-
経営理念
いつでも、どこでも、何度でも、楽しく効果的なリハビリが行えるシステムを構築する
【開発背景と解決課題】
現在、WHO によればなんらかの障害をもつ人口の割合は国内外で 30%、リハビリが必要な人口は世界で 24 億人と言われており、リハビリへの需要は急速に高まっている。国内を見ても高齢化のみならず特別な支援が必要な子どもの数は増加傾向が続き、医療機関・地域コミュニティ双方にて障害児者への専門的なリハビリサービスの提供が求められている。
現状のリハビリにおける課題として、主に以下の 3 点が挙げられる。
1 単調で伝統的な臨床技術が根強く、当事者のモチベーションが上がりづらい
2 適切なリハビリの量が提供できていない
3 根拠に基づく介入(Evidence-based Practice:EBP)より、支援者の経験則が優先されやすい
弊社は、<いつでも、どこでも、何度でも、楽しく効果的なリハビリが行えるシステムを構築する>ことを通じて、上記の社会課題解決を目的に活動を行っている。
【目の前のたった 1 人から始まった開発】
前述の社会課題に着目したのは、弊社創業メンバーの 1 人が<福山型筋ジストロフィー>と呼ばれる先天性疾患をもつ娘のリハビリに疑問を感じたのがきっかけであった。
リハビリのたびに泣いて嫌がる娘を見ながら、健康のために必要なリハビリでも、楽しく本人が望む形で行いたいと考えるようになった。
【当事者家族と医療福祉専門職がチームを構成】
たった 1 組の当事者親子から始まったプロジェクトであるが、現在はそこに作業療法士や理学療法士など、リハビリの国家資格と臨床経験を有するメンバーが参画し、当事者性と専門性を有するハイブリッドチームが実現している。エンジニアも作業療法士の資格を有しており、企画構想から販売、アフターフォロー、開発までを一貫して自社で提供していることが特徴である。
-
経営理念に基づいて、具体的に取り組んでいること
リハビリをより楽しく、効果的なものに拡張する障害児者向けデジタルリハビリツール「デジリハ」の運用
障害児者向けデジタルリハビリツール「デジリハ」はリハビリをより楽しく、効果的なものに拡張することを目的に、障害児家族及び医療福祉専門職によって完全開発されている。デジリハは、ゲーム感覚で実施できるアプリ、複数のセンサーと連動するカスタマイズ機能、そしてデータベースにて構成されている。
2021 年春のリリースから、現在約100件以上の医療機関(総合病院、リハビリ専門病院)、福祉施設(放課後等デイサービス、児童発達支援事業所、生活介護等)、教育機関(特別支援支援学校)で導入されている。後述のように、デジリハ開発当初のターゲットは障害をもつ子どものリハビリであったが、現在は脳卒中患者へのリハビリ等、成人や高齢者の方にもご活用いただいている。
紹介動画 URL:https://youtu.be/Sa3Cum68xLg?si=Q7zNIlVE7pHlOFJ-
【デジリハの特徴】
特徴1:幅広い障害種及び目的に利用可能
リハビリは粗大運動から巧緻運動、協調性など多くの要素を含み、かつ対象となるエンドユーザーの特性も非常に多様である。一般的には特定の疾患や目的にのみ対応するリハビリツールが多いが、デジリハは多様なセンサー、30 本以上の多彩なアプリ、そしてカスタマイズ機能を活用して多くの対象者、目的に適応可能である。
特徴2:専門職によるアフターフォロー・ユーザーコミュニティ
ユーザー同士の学び合いの場や問題解決型思考をトレーニングするカリキュラム、「デジリハ ACADEMY」の提供など、デジリハ活用を発展させるアフターフォローを積極的に提供している。
特徴3:学術活動、共同研究の積極展開
医療、福祉、教育など幅広い領域において、教育機関や研究機関とともに共同研究を積極的に推進してい
る。加えて、ユーザーとともに実際の利用現場における効果検証を行うための学術サポートも提供。医療・福祉・教育における根拠に基づいた支援の提供に貢献している。
-
今後のビジョンや展望など
エビデンス構築を促進し、EBP の実践を支援するデータベースへの展開
【今後の製品強化予定】
1. エビデンス構築を促進し、EBP の実践を支援するデータベースへの展開
現在データベースではプレイスコアやセンサーデータの閲覧が一部可能となっているが、今後は国際標準化されている評価指標を加えて蓄積、分析が可能なものとしていく。同データに対し、年代別の標準範囲を算出し、ダッシュボードにて視覚的に閲覧が可能なものとする。
アプリを継続的にプレイすることで、障害児者の支援に重要な機能、活動、参加に関する包括的・経時的データを閲覧することができる。
2. toC サービスの展開
現在の施設向けサービスに加え、障害児者がご自宅でプレイできる toC サービスを展開予定である。同サービスではカスタマイズ機能など施設向けのサービスの特徴を引き継ぎつつ、スマホやタブレットなど簡易デバイスで利用できるものを想定している。
個人ユーザーと施設ユーザーはアカウントで紐づいており、ダッシュボードを通じて相互にリハビリ実施状況の確認や機能変化の共有が可能となる。
これら 2 点の強化を行うことにより、下図に示す長期インパクトを創出していく。
-
取り組みにより、どのような社会的インパクトを起こしてきましたか
計100件以上の医療・福祉・教育機関に「デジリハ」を導入
現在までで計100件以上の医療・福祉・教育機関に導入いただいており、日常的なリハビリにおいて利用が進んでいる。その中での大きな社会的インパクトは以下の2点である。
①障害児者における心身の機能に対するインパクト
幅広い障害児者のニーズに対しデジリハを適応した際の具体的な変化について、複数の研究機関や導入事業所から研究発表をいただいている。
定型発達児における追視や注視を行うゲーム施行中の眼球運動/髙橋恵里(福島県立医科大学)
視覚関連の症状がある児童に対するアイトラッカーを用いたデジリハアプリでの介入効果/吉野ゆい(アスノバ放課後等デイサービス)
②障害児者へのサービスを提供する支援職のスキルに関するインパクト
さらに、デジリハを導入することによる支援職(教員、医療福祉専門職、学生など)の支援提供スキルの向上や行動変容についても複数の学会発表などが進んでいる。
デジタルトランスフォーメーションにおけるリハビリ人材の育成に関する検討/西村昭宣(琉球リハビリテーション学院)
自立活動におけるICT(デジリハ)活用の効果と課題 ー特別支援学校(肢体不自由)教師に対するインタビュー調査をもとにー/八柳千穂(水戸特別支援学校)
-
今後のビジョンや展望により、どのような社会的インパクトが期待できますか
デジリハの継続利用による障害児者の経時的な変化を定量化・見える化する
今後社会的インパクトの観点で特に重要となってくるのは、前述のデータベース・ダッシュボード機能である。デジリハの継続利用による障害児者の経時的な変化を定量化・見える化することにより、支援の効果判定の質を向上させることが可能となる。リハビリや医療福祉における障害児者支援では効果判定が曖昧になってしまうことが多いので、このような定量的な評価を支援職のスキルを問わず実施可能とすることは、障害児者への大きな利益となる。
加えてデータベースを発展させていくことで、国内外の障害児者情報を網羅したプラットフォームとして機能することが可能となる。現在障害児者の包括的データベースは行政も所持出来ていないものであり、これを各行政と連携することができれば、医療福祉関連財源の配分もより効率的に実施することに寄与できる。
-
従業員・顧客・取引先への配慮
障害の有無や家族の状況などで就労をあきらめてほしくない
障害の有無や家族の状況などで就労をあきらめてほしくないため、ソーシャルファームに申請中です。
人事考課制度も取り入れています。
顧客へは定期的に連絡、ヒアリングを行い開発へ生かしています。
-
地域社会への配慮
特別支援学校へのアプリの無償提供など
・特別支援学校では、関心あるものの予算がないとの声が多かったため、アプリの無償提供を行った。同時に、アプリ使用のためのハードウェア機材は休眠預金等活用事業資金分配団体の一般財団法人リープ共創基金から支援を受け、2年間無償貸与を実施。
関東圏のプロジェクトだったが、関西圏でも同様のスキームでできないか検討中。
・九州の医療福祉専門学校の生徒とデジリハを用いたプログラムを立案し、実際に支援学校や事業所で試行する実践型学習を実施。京都医健でも同様の取組ができないか検討中。
・京都市リハビリテーションセンターと連携し、体験デモ会を実施。 -
環境(未来の社会)への配慮
リハビリを必要とする子供たちがいきいきと楽しく取り組める社会を目指していく
事業の取組や共同研究の内容等はHPで定期的に配信している。当社の事業を国内外に広げ、リハビリを必要とする子供たちがいきいきと楽しく取り組める社会を目指していく。